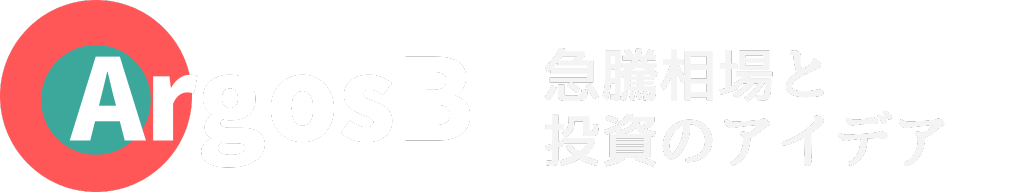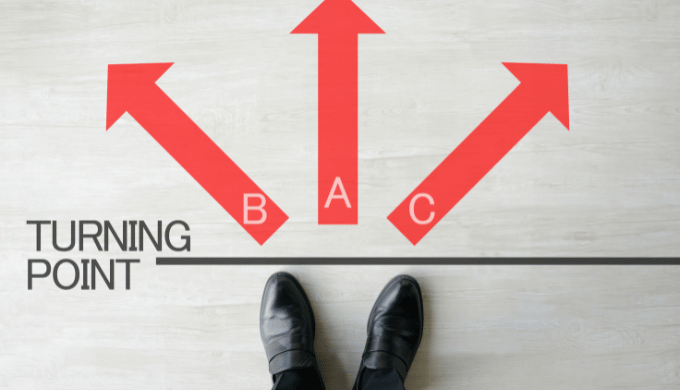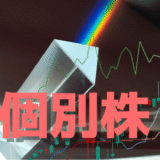個別株投資では、景気や経済、政治、為替、金融政策など、マーケット全体の動向を把握することが不可欠です。これらの要因は相互に影響し合い、投資家心理や短期マネーの流れに影響を与えています。投資機会を活かすためには、こうした外部環境や市場心理をしっかりと理解することが、物色トレンドを見極めるうえで非常に重要です。
今週(9月22日~)の海外市場は、FOMCや日銀といった主要イベント通過後という背景から小動きが目立っています。しかし今年春以降の株式市場を振り返ると、外国人投資家の買いが徐々に鮮明になってきました。
彼らが日本株を本格的に買い始めると、過去の経験則では半年から1~2年にわたり資金を投じ続ける傾向があります。これは、海外投資家が年金基金や大型ファンドを背景に長期の運用方針をとることや、一度ポジションを取った後に短期で離脱すると市場に大きなインパクトを与えるため、腰を据えた投資を行う傾向があるためです。
実際に、2013年からのアベノミクス相場では外国人投資家が長期にわたり買い越しを続け、2020年のコロナパンデミック直後にも大規模な資金流入が確認されました。今、その兆しが再び現れつつあり、投資家の関心が高まっています。現在の日本株市場ではどのような動きが進んでいるのでしょうか。
2024年春頃から散見されていた打診的な買いは、2025年春以降に連続した買い越しへと発展し、今の局面を形作っています。外国人投資家は2025年3月末から6月下旬にかけて日本株の現物を13週連続で買い越し、累計でおよそ4兆4,000億円に達しました。これは短期的な様子見を超え、中期的で持続性のある資金流入と位置づけられます。
またこれに次いで、8月第2週には1週間で1兆7,503億円の買い越しが記録されたことは、海外勢の積極的な投資姿勢を示しています。個人投資家が売り越し基調にある一方で、外国人投資家が市場を下支えしている状況です。こうした連続的な買い越しは、ここ10~12年を振り返っても極めて稀で、歴史的に注目される動きとなっています。
最近、海外メディアで注目されている「Takaichi trade」(高市トレード)も投資家の期待感を高める要素です。国内では一般的な用語として定着しているわけではありませんが、海外投資家やメディアが政策期待を織り込む際に用いられている表現で、その関心の高さが窺えます。自民総裁選で高市氏が掲げる積極財政や集中投資といった政策は、市場にとって成長期待を強める材料となり、海外投資家の間では円安や株高を促すとの見方が広がっています。政策関連株やインフラ、不動産関連株が恩恵を受けやすいとされ、こうした動きが大型株中心に先行することで、やがて中小型株や材料株にも波及する余地があります。
さらに、グロース市場など中小型株への影響も無視できません。海外投資家が大型株を中心に買い進めることで市場全体の地合いが改善すると、相対的に値動きの軽い中小型株や材料株にも資金が波及しやすくなります。
現状はまだ、その兆候は見られませんが、先行する大型株買いの動きが一服すると、中小型株への資金シフトが鮮明になる可能性があります。数週間から数か月のスパンで売買する投資家にとっては、短期的な物色機会がさらに拡大する点が注目されます。
一方で、海外投資家の日本株全体を買う動きが本格化したと断定するには時期尚早です。為替や金利、米国の利下げ観測、国際情勢など不透明な要素は依然として残っており、資金流入の持続を妨げる可能性があります。
ただし、欧米市場と比べ割安感が強い日本株では、テーマ性や割安感を備えた銘柄に資金が着実に流入しており、本格化の兆しはむしろ強まっていると言えます。連続買い越しの反動で短期的な調整が入るリスクは残るものの、全体としては上昇トレンドへの期待感を高める局面であり、今後の動向に注目が集まります。
総じて、現在は打診的な買いから本格的な買いへの移行期にあると考えられます。慎重に始まった投資が資金の積み増しへと進んでいる様子も確認できます。ただし、まだ全面的に安心できる段階ではなく、今後の市場環境や世界的な金融政策の行方が、外国人投資家の日本株買いを確固たるトレンドに押し上げるかどうかを決定づけることになるでしょう。